小鳥のさえずりで目を覚ますのはいつものことだ。
しかしふだんと違うのは、体がとても温かいということ。森の朝は冷えるというのに、今日はどうしてか寒さをまったく感じない。
(――っ!!)
ゆっくりとまぶたを開けたリルは大声を出しそうになって、あわてて口もとを押さえてこらえた。
目の前には白金髪の王子様。すうすうと静かな寝息を立てて眠っている。オーガスタスの腕はリルの腰にしっかりと巻きつき、またリルの腕も同じだった。
彼を抱き枕と勘違いしていたようで、むき出しの胸を押し付けるようにきつく抱きしめてしまっていた。
そろそろと腕を前にもってきてオーガスタスから距離をとる。彼の腕には思ったほど力が入っておらず、ベッドから抜け出すのは簡単だった。
裸のままベッドわきから王子を見つめる。
(まるで造りものみたい)
寝息が聞こえていなければ、蝋人形かなにかと間違えてしまいそうだ。
顔の造作はひとつひとつが美しく、全体のバランスもよい。ひとではなく、美しい絵画をいつまでも見ていたくなるのと同じような心境に陥ってしまう。
(それにしても無防備ね)
寝ているのだからあたりまえだが、布団にくるまって眠る姿はどこかかわいらしくもあった。
(……っと、いけない。パンを焼いて、洗濯をして、それから)
朝やるべきことはたくさんある。リルはクローゼットから普段着のドレスを取り出して身につけてエプロンを羽織り、パン作りを始めた。
ベッドとキッチンは部屋の対角線上にあり、もっとも離れてはいるがそれでも音を立てて彼を起こしてしまわないように気を配った。
パン生地をこね、発酵させているあいだにテラスで洗濯をする。発酵が終わったパンをオーブンに入れて焼き、そのあいだにふたたびテラスへ向かって洗濯物を干した。
焼き上がったパンを網のうえに乗せてから、裏庭の野菜を採りにいった。
「おはよう、リル。早いんだね」
トマトやきゅうりを採取していると、小窓からオーガスタスが顔を出してそう言った。リルは野菜を持ったまま答える。
「ええ、おはよう。待っててね、すぐに朝食にするから」
「うん。僕、お腹ぺこぺこだよ」
猫なで声でそう言われれば、母性が刺激される。リルはいつにも増して、てきぱきと庭の野菜を採って屋敷のなかへ戻った。
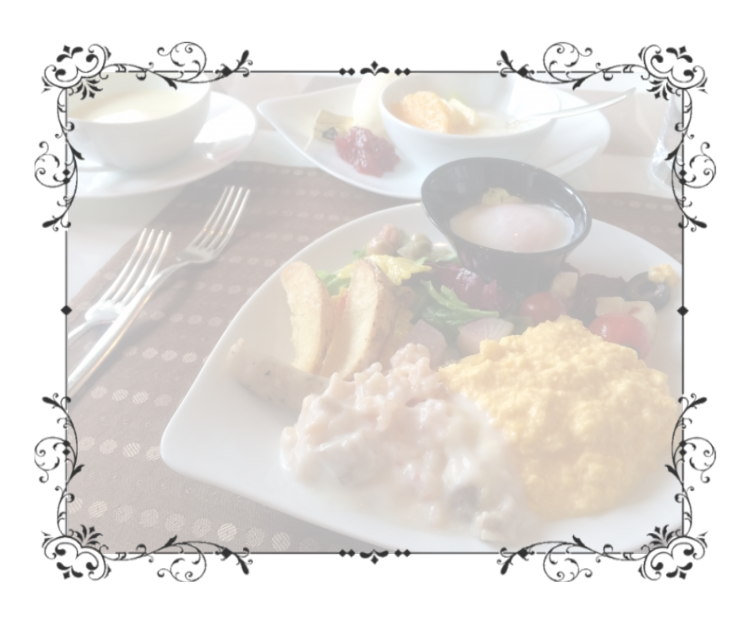
「すごい、おいしそう!」
感嘆の声を上げるオーガスタスだが、リルは目を合わせることができなかった。
「どうぞ、召し上がれ。……その、ごめんなさいね。裸で朝食なんて」
「ん、べつにかまわないよ。むしろ僕のほうが謝るべきだね。見苦しくてごめん」
四角いダイニングテーブル前の椅子に、オーガスタスは裸で座っていた。厳密に言うと、腰にバスタオルだけを巻いた状態だ。彼の服は先ほどすべて洗ってしまった。
「見苦しくなんてないわ。だって、すごく綺麗だから」
言ってしまったあとで後悔した。男の裸を愛でるなんて、淑女のすることではない。
「あ、ええと、違うの。その……」
言いよどむリルをよそにオーガスタスはパンを口に運び、もぐもぐとおいしそうに頬張った。
「じゃあ、リルも脱いで」
「なっ、なんでそうなるのよ!」
「だって、僕もリルの綺麗な体を見ながら食べたいし。ね? 早く」
「………」
リルは無言で頬を赤く染め、フォークで野菜サラダをつついた。視線をさまよわせながら食べ進める。
「赤くなっちゃって、かわいいなぁ。リルは」
「……あなたは全然かわいくないわ。少しは恥ずかしくないの?」
彼は裸で食事をしているというのに、羞恥心のかけらも見受けられない。
「んー、そうだなぁ……。リルが裸にエプロンだけを着てくれたら、興奮して真っ赤になっちゃうかも」
「ぐっ、こほっ!」
「わっ、大丈夫?」
トマトが逆流してきそうになるのをなんとか押しとどめ、飲み込む。
「だ、大丈夫じゃ、ない……! い、いったいなにを、言ってるの!」
「だから、そのドレスをすべて脱いでエプロンだけを着るんだ。さっきまで着てたよね、かわいらしいピンク色のエプロンを」
オーガスタスは横目でちらりとキッチンを見やった。キッチンわきの小さな円卓のうえに、たたんで置いてあるエプロンを目線で示している。
「だっ、だから! そんなことするわけないでしょう。あんまりへんなことを言うと、取り上げるわよ」
彼の前にある皿を両手で引く。するとオーガスタスはあわてたようすで皿をつかんだ。
「ごめん、ごめん。冗談だよ。うーん、それにしてもおいしい。ほっぺが落ちそうだ」
それからオーガスタスは過剰にリルの朝食を褒めちぎり、パンやサラダを性急に腹のなかへ入れていった。
前 へ
目 次
次 へ
しかしふだんと違うのは、体がとても温かいということ。森の朝は冷えるというのに、今日はどうしてか寒さをまったく感じない。
(――っ!!)
ゆっくりとまぶたを開けたリルは大声を出しそうになって、あわてて口もとを押さえてこらえた。
目の前には白金髪の王子様。すうすうと静かな寝息を立てて眠っている。オーガスタスの腕はリルの腰にしっかりと巻きつき、またリルの腕も同じだった。
彼を抱き枕と勘違いしていたようで、むき出しの胸を押し付けるようにきつく抱きしめてしまっていた。
そろそろと腕を前にもってきてオーガスタスから距離をとる。彼の腕には思ったほど力が入っておらず、ベッドから抜け出すのは簡単だった。
裸のままベッドわきから王子を見つめる。
(まるで造りものみたい)
寝息が聞こえていなければ、蝋人形かなにかと間違えてしまいそうだ。
顔の造作はひとつひとつが美しく、全体のバランスもよい。ひとではなく、美しい絵画をいつまでも見ていたくなるのと同じような心境に陥ってしまう。
(それにしても無防備ね)
寝ているのだからあたりまえだが、布団にくるまって眠る姿はどこかかわいらしくもあった。
(……っと、いけない。パンを焼いて、洗濯をして、それから)
朝やるべきことはたくさんある。リルはクローゼットから普段着のドレスを取り出して身につけてエプロンを羽織り、パン作りを始めた。
ベッドとキッチンは部屋の対角線上にあり、もっとも離れてはいるがそれでも音を立てて彼を起こしてしまわないように気を配った。
パン生地をこね、発酵させているあいだにテラスで洗濯をする。発酵が終わったパンをオーブンに入れて焼き、そのあいだにふたたびテラスへ向かって洗濯物を干した。
焼き上がったパンを網のうえに乗せてから、裏庭の野菜を採りにいった。
「おはよう、リル。早いんだね」
トマトやきゅうりを採取していると、小窓からオーガスタスが顔を出してそう言った。リルは野菜を持ったまま答える。
「ええ、おはよう。待っててね、すぐに朝食にするから」
「うん。僕、お腹ぺこぺこだよ」
猫なで声でそう言われれば、母性が刺激される。リルはいつにも増して、てきぱきと庭の野菜を採って屋敷のなかへ戻った。
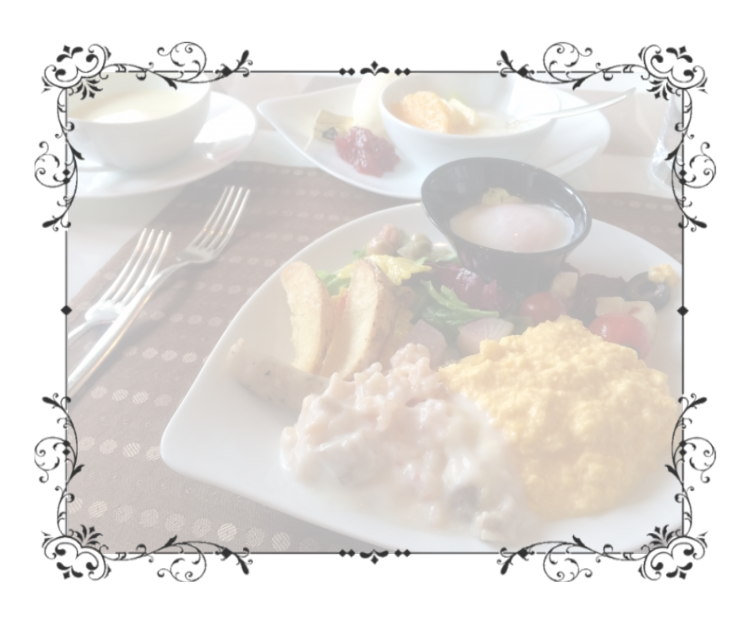
「すごい、おいしそう!」
感嘆の声を上げるオーガスタスだが、リルは目を合わせることができなかった。
「どうぞ、召し上がれ。……その、ごめんなさいね。裸で朝食なんて」
「ん、べつにかまわないよ。むしろ僕のほうが謝るべきだね。見苦しくてごめん」
四角いダイニングテーブル前の椅子に、オーガスタスは裸で座っていた。厳密に言うと、腰にバスタオルだけを巻いた状態だ。彼の服は先ほどすべて洗ってしまった。
「見苦しくなんてないわ。だって、すごく綺麗だから」
言ってしまったあとで後悔した。男の裸を愛でるなんて、淑女のすることではない。
「あ、ええと、違うの。その……」
言いよどむリルをよそにオーガスタスはパンを口に運び、もぐもぐとおいしそうに頬張った。
「じゃあ、リルも脱いで」
「なっ、なんでそうなるのよ!」
「だって、僕もリルの綺麗な体を見ながら食べたいし。ね? 早く」
「………」
リルは無言で頬を赤く染め、フォークで野菜サラダをつついた。視線をさまよわせながら食べ進める。
「赤くなっちゃって、かわいいなぁ。リルは」
「……あなたは全然かわいくないわ。少しは恥ずかしくないの?」
彼は裸で食事をしているというのに、羞恥心のかけらも見受けられない。
「んー、そうだなぁ……。リルが裸にエプロンだけを着てくれたら、興奮して真っ赤になっちゃうかも」
「ぐっ、こほっ!」
「わっ、大丈夫?」
トマトが逆流してきそうになるのをなんとか押しとどめ、飲み込む。
「だ、大丈夫じゃ、ない……! い、いったいなにを、言ってるの!」
「だから、そのドレスをすべて脱いでエプロンだけを着るんだ。さっきまで着てたよね、かわいらしいピンク色のエプロンを」
オーガスタスは横目でちらりとキッチンを見やった。キッチンわきの小さな円卓のうえに、たたんで置いてあるエプロンを目線で示している。
「だっ、だから! そんなことするわけないでしょう。あんまりへんなことを言うと、取り上げるわよ」
彼の前にある皿を両手で引く。するとオーガスタスはあわてたようすで皿をつかんだ。
「ごめん、ごめん。冗談だよ。うーん、それにしてもおいしい。ほっぺが落ちそうだ」
それからオーガスタスは過剰にリルの朝食を褒めちぎり、パンやサラダを性急に腹のなかへ入れていった。
